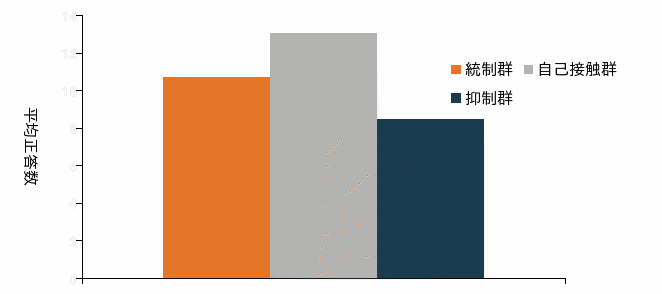~注意制御における自己接触行動の役割~
2025年9月16日
早稲田大学
発表のポイント
●自分の顔や体の一部を触るといった「自己接触行動※1」が、言葉を探したり思い出したりする際(語彙検索)の助けになることを実験で明らかにしました。
●顔への自己接触行動は、外部からの余計な刺激を遮断し、特定の課題への注意を維持することを助けると考えられます。
●自己接触行動は、集中が必要とされる場面や騒音・雑音がある場面などで、注意の制御や認知処理に役立つと考えられるので、教育や日常生活でのコミュニケーション改善に応用できると期待されます。
図1.正答数の結果と実験条件(誤差線は標準誤差)
人はなぜ顔を触るのか?
人が言葉を探すときに顔を触るのは、単なる癖やかゆみの緩和ではなく、実は言葉を思い出すことを助けていることがわかりました。早稲田大学人間科学学術院の関根 和生(せきね かずき)准教授と早稲田大学人間科学部(研究当時)の堀田 浩史(ほった ひろし)氏らの研究グループは成人を対象に、ことわざや四字熟語の定義を問い、それに対応する言葉(ことわざ・四字熟語)を答えるという課題を実施しました。
結果として、自己接触(頬に手を当てる)をしながら課題に取り組んだ参加者は、手の動きを抑えるように指示された参加者よりも正答数が多い結果となりました。これは、顔を触る動作が、特定の課題に対する注意制御※2に役立っていることを示唆しています。
本研究成果は、2025年8月26日(火)に『Languages(MDPI)』に掲載されました。
キーワード:
自己接触、語彙検索、注意制御、認知処理、コミュニケーション
(1)これまでの研究で分かっていたこと
人が会話や課題に取り組む際には、言葉だけでなく身振りや表情といった非言語的行動が伴います。その中でも「自己接触行動」と呼ばれる、顔に手を当てる、髪を触る、腕を組むといった行動は、意図的な情報伝達を目的としない点で特徴的です。1960年代にEkmanとFriesenが自己接触行動を体系化して以来、心理学では自己接触がストレスや緊張を和らげる働きを持つと考えられてきました。例えば、人前で発表する際に無意識に顔を触るといった行動がその一例です。
その後、研究は情動調整だけでなく認知処理との関係にも広がりました。Barrosoらはストループ課題※3において自己接触が増えることを報告し、注意制御や負荷との関連を指摘しました。さらに、日本の藤井(1997)はことわざや四字熟語を用いた実験で、自由に手を動かせる参加者の方が正答数が多いことを示し、思い出したい言葉が「のどまで出かかっている状態(Tip-of-the-Tongue:TOT状態※4)」で自己接触行動が増加することを観察しました。加えてPineら(2007)は子どもを対象に調査を行い、言葉が思い出せない状態(TOT状態)で自己接触が増えることを報告しています。
このようにこれまでの研究では、自己接触行動が語彙検索を助ける可能性が論じられてきました。しかし、いずれの報告も観察にもとづいたもので、自己接触行動を実験的に操作することはしませんでした。そのため、自己接触行動が「本当に言葉を思い出す助けになっているのか」を実証的に確かめる必要が残されていたのです。
(2)今回の新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと、そのために新しく開発した手法
本研究グループでは、「顔を触る行動」が言葉を思い出すことに役立つのかを検証しました。これまで、この行動は緊張や注意の調整に関係すると言われてきましたが、効果を直接確かめた研究は少数でした。対象は日本語を母語とする成人60名(男女同数、平均20歳)です。参加者はことわざや四字熟語の定義を聞き、その定義に対応する言葉を答える課題に取り組みました。この課題中に言葉が「のどまで出かかっている」のに思い出せない状態(TOT状態)になったら、それを報告してもらうように指示しました。
実験では3つの条件を比較しました。①手の動きに関して特に教示をしない「統制条件」、②両手で頬を触りながら課題に取り組む「自己接触条件」、③棒を両手で持ち手を動かせなくさせる「抑制条件」の3条件です。回答は「正答」「誤答」「TOT後の正答」「TOT後の失敗」に分類し、さらに課題終了後には思い出せる限りのことわざや四字熟語を書き出してもらいました。結果は明確でした。自己接触条件は抑制条件より正答数が有意に多く、自己接触行動が語の想起を助けることが示されました。一方、TOT状態からの解決率には条件間の差がみられませんでした。
統制条件を対象に行なった映像分析からは、自己接触は全体を通じて多く観察され、ジェスチャーは特にTOT状態で増えることが確認されました。これはジェスチャーが「特定の意味を作り出す助け」として機能し、自己接触は「特定の課題に注意を向けるための戦略」として働くことを示唆します。今回の工夫は、従来の統制条件と抑制条件に加え、新たに「自己接触条件」を導入したことです。図1が示すように、自己接触条件は統制条件と同程度の成績を示し、抑制条件より明らかに高い結果となりました。これにより、人が無意識に行う「顔を触る」といった行動が、単なる癖ではなく、認知過程を支える身体的戦略である可能性が強く示されました。
(3)研究の波及効果や社会的影響
本研究は、無意識に行われる自己接触行動が言葉を思い出す過程を助けることを、初めて実験的に示しました。この成果は、日常生活で誰もが経験する「言葉が出てこない状態」の理解を深めるとともに、言語研究に新しい視点を提供します。
社会的な効果としては、まず高齢者や失語症者など、語想起の困難を抱える人々への支援に応用できる可能性があります。年齢とともに増える「言葉が出にくい場面」において、自己接触行動を自然に取り入れることで、会話を続けるための手がかりや安心感を与えることが期待されます。特に、雑音や騒音など、気が散りやすい場面において、自己接触行動を行うことで、現前の取り組むべき課題(今回の場合では語彙検索)に注意が向けられ、妨害的なノイズを心理的に除去できると考えられます。
学術的な効果としては、これまで主に「意味を伝えるジェスチャー」に注目してきた心理学や言語学の研究に対し、非伝達的な身体動作の意義を示した点が挙げられます。自己接触行動は「注意や認知の制御」に関与する可能性があり、ジェスチャーとは異なる役割を担っています。この違いを明確に区別して研究することで、人間の言語生成や認知過程の理解がさらに深まることが期待されます。
(4)今後の課題、展望
本研究では、自己接触行動が言葉を思い出す過程を助けることを示しましたが、いくつかの課題が残されています。まず、本研究の参加者は若年成人に限られており、年齢や文化の違いによる影響は明らかになっていません。また、ことわざや四字熟語といった特定の刺激を用いたため、日常会話にそのまま当てはまるかどうかには検討の余地があります。今後は、高齢者や子どもを対象とした研究、より自然な会話場面での検証が必要です。さらに、脳活動の計測などを組み合わせることで、自己接触行動がどのように注意や記憶を支えているのかを解明できると考えられます。こうした研究の積み重ねにより、教育や高齢者支援など社会的応用の可能性が広がると期待されます。
(5)研究者のコメント
人は言葉に詰まったとき、自然に顔や体を触ります。これまで単なる癖と考えられてきた行動が、実は言葉を思い出す助けになることを実証しました。この成果は、私たちの「からだ」が表現だけでなく思考や会話を支えていることを示しています。今後もこの知見を活かして、コミュニケーションや言語習得の支援への応用を目指して研究を進めていきます。
(6)用語解説
※1 自己接触行動:
人が無意識に自分の体に触れるしぐさを指します。たとえば、顔に手を当てる、髪をさわる、指をこするなどがあります。これまでは緊張や不安をやわらげる行動と考えられてきました。
※2 注意制御:
自分の注意を必要な対象に集中させたり、不要な情報を無視したりする心の働きを指します。勉強や会話をスムーズに進めるために欠かせない機能です。
※3 ストループ課題:
単語の意味と文字色が一致または不一致の刺激を提示し、参加者にインク色を答えてもらうことで、注意制御能力、特に無関係な情報を抑えて必要な情報に集中する力を調べる心理学的課題です。
※4 TOT状態(Tip-of-the-tongue state):
言葉が「のどまで出かかっている」のに思い出せない状態を指します。
(7)論文情報
雑誌名:Languages(MDPI)
論文名:The Role of Self-Adaptors in Lexical Retrieval
執筆者名(所属機関名): 関根 和生*(早稲田大学 人間科学学術院)、堀田 浩史(早稲田大学 人間科学部)(研究当時) *責任著者
掲載日時:2025年8月26日(火)
DOI:https://doi.org/10.3390/languages10090209
掲載URL:https://www.mdpi.com/article/10.3390/languages10090209