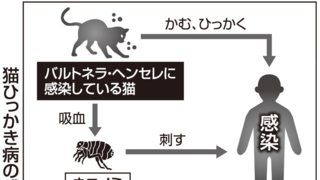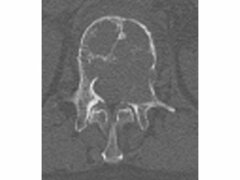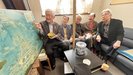岐阜大学精神科医 塩入俊樹氏
かつて「発達障害」の中でも、特に「自閉症スペクトラム障害(ASD)」や「注意欠如・多動性障害(ADHD)」は小児・思春期の疾患で、大人になれば症状は自然と消失するか、目立たなくなると思われていました。
しかし1990年代になると、症状は成人になってもかなりの程度持続し、抑うつや不安などの二次的な症状も伴い、重篤な社会不適応状態を呈してしまうことが分かりました。わが国では、大人の「発達障害」について、当初はASDの存在がクローズアップされましたが、近年、ADHDの問題も注目されています。それを受け、政府は2016年に発達障害者支援法の改正を行い、「発達障害」においては、子供から大人までのライフステージを通じた、切れ目のない支援をその目的・基本理念としました。
受診のきっかけは、職場など周囲から勧められた場合や、うつ病や不安障害などの他の疾患があって受診する場合が多いようです。その経過は大きく二つあります。一つは、子供の頃から「発達障害」の診断がされていて、引き続き悩んでいる場合。もう一つは、子供の頃には問題がなく、あるいは程度が軽く、大人になってから初めて「発達障害」の診断がついた場合です。特に、後者の患者(ASDとADHD)が急増していると言われています。
これらの患者は、本来は「発達障害」の特性は持ち合わせていたものの、知的レベルや周囲のサポートが十分にあり、ある程度の枠組みが決まった日常生活では、家庭・学校でも目立った問題はなく、対人関係でも大きなトラブルもなく過ごせました。当然、子供の頃に診断はつきません。
ところが大人になって、就職などで社会に出た際、複雑化した対人関係や社会生活の中で初めて問題が顕在化(失業や社会的孤立、多額の借金、進学の問題、結婚・出産など)し、受診に至るのです。
実は、大人の「発達障害」で問題になるのは診断がより困難なことです。「発達障害」としての症状は軽いのに比べ、社会的不適応による自信喪失、自己評価や自尊心の低下から、抑うつや不安などの二次的な症状が主訴となり、「発達障害」そのものの症状が隠れてしまっています。
さらに保護者の高齢化などで「発達障害」の診断に欠かせない幼少期からの詳細な情報も聞き取りが難しくなります。その困難さは"精神科医泣かせ"と言っていいでしょう。このような場合、数回以上の継続した診察が必要となります。
大人の「発達障害」に対する治療も、子供に対する薬物療法や支援体制と基本は変わりません。しかし、支援の受け皿が会社となると、子供ほどのサポート体制がないのが現状です。患者が本来持っている能力は、適切な治療により十分発揮することが可能です。個々の違いを「個性」として捉え、全ての人たちが共存できる"真のノーマライゼーション社会"を目指したいものです。
(岐阜大学医学部付属病院教授)