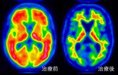季節外れの暖かさが一服したのを見計らい、倉庫から特注の木おけを運び込む。岐阜市の長良川河畔に立つ老舗旅館「十八楼」。1日300人の利用客の食事を賄う広い厨房(ちゅうぼう)の一角で、「鮎のなれずし」が漬け込まれていく。
「空気を抜くように、炊きたてのご飯をギュッと詰めていきます」。料理長の西岡功さん(53)の傍らには、腹を割って内臓を抜き、塩漬けと塩抜きを経た天然鮎が並ぶ。
使うのは、背が黒く柿色の婚姻色を帯びた秋の落ち鮎。脂が抜けた方がよいとされるためで、昆布巻きに子持ちの雌が好まれるのに対し、なれずしは身がしっかりした雄を用いる。
おけに重ねて並べ、1カ半から2カ月ほど常温で発酵させると、伝統の逸品が出来上がる。「置いておくだけ。不思議なもんです」
この地方の鮎ずしは、古くは平安時代の法制書「延喜(えんぎ)式」に美濃国の「年魚鮨」「鮨年魚」として登場する。江戸時代には、岐阜町から笠松を経る「御鮨街道(おすしかいどう)」で幕府に献上された。
長良川鵜飼の鵜匠の山下家に伝わる「鵜匠家由緒書」には、大坂夏の陣の帰途に鵜飼を見た徳川家康と秀忠の父子が、鮎ずしを「十度」お代わりしたとの逸話が書かれている。献上の始まりは諸説あるが、「この年の1615年から幕府御台所の御用になっている。鮎ずしを気に入ったのだろう」と長良川うかいミュージアム(岐阜市)の河合昌美学芸員は指摘する。
「長良川鵜飼習俗調査報告書Ⅱ」によると、献上鮎ずしは「御鮨所」の河﨑家が夏に作り、出荷も担った。現在、鵜匠各家は冬場の贈答用に漬けており、献上鮎とは漬け込む時期や期間が異なるが、近代以降の製法をほぼ同じ形で受け継いでいるとみられている。
西岡さんが作るようになったのは、7年前。岐阜長良川温泉旅館協同組合の料理長会で「鵜匠の家すぎ山」の森保夫料理長から教わったのがきっかけだった。「私たちにとっては秘伝ではなく、『当たり前』のものだから」と鵜匠家と血縁の杉山貴紀社長(44)。のれんを超えた協力が長良川の観光振興につながることを期待する。
組合のうち旅館の5軒が、懐石の一品やメニューに載せない形で、時期によって提供している。味がそれぞれ異なるのは、まさに発酵の妙。西岡さんは今季、約200匹を仕込む。「岐阜ならではの味を、歴史と共に味わってほしい」と願っている。