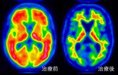昔ながらの商家が残る旧中山道御嶽宿の一角。奥まった台所でガス釜のふたを開くと、湯気とともにサンマ独特の芳香が広がった。郷土料理「さより飯」が炊き上がった。
「できた、できた」。笑顔の丹羽春子さん(84)=可児郡御嵩町=が、しょうゆで色づいたご飯の上で光り輝く筒切りの身から、骨を外す。骨のまま炊くと味が出るのだという。
青果や鮮魚を扱う食料品店「マルヒチ」を家族で営む。作り方を教えてくれた義母ときさんは、面倒見がよく、人を寄せるのが好きだった。「『サンマがようけ来るなあ、いっぺん炊こか』ってね」。集まりが無くても、どっさり作ると、丼を手に親戚が取りに来た。
戦中、戦後の食糧難を知る春子さんの夫常勝さん(89)にとっても、ごちそうだった。「炊いてくれたのは、年にいっぺんか、二へん。うれしかったね。骨も食べよった」
「さより飯」は中濃から東濃にかけ、かつて作られた炊き込みご飯。名称は細長い魚形にちなむ。明治末期から大正初期の暮らしを記した「御嵩町史民俗編」によると、「えべすこ」「しこう」など人が集う諸行事で作られた。
1939年の宮内省(当時)の全国郷土料理調査で「日本五大名飯」にも選ばれたとされるが、農村の行事が姿を消し、核家族化が進む中で、いつしか忘れられていった。
そこで、道の駅「可児ッテ」(可児市柿田)は、名物に育てようと、2010年の開業時からパック詰めを販売した。懐かしむ声の一方、苦情が寄せられた。「小骨が刺さったらどうする」
せっせと小骨を抜いたり、臭みを取る工夫をしたり。アレンジを繰り返したが、手間がかかる。「地域の食文化だし、売れる条件はそろっているのに……」と纐纈直樹駅長(60)。サンマの高騰もあり、5年前に販売を打ち切った。
もはや幻の味。それを東濃実業高校(御嵩町)の生徒たちが昨年、復活させた。鮎の甘露煮などを製造販売する「鵜舞屋」(岐阜市)の提案を受けたコラボレーション商品は、骨まで食べることができ、具材も豊富。今年の商品を手掛けた立川ななせさん(18)は「魚の風味がよくて、すごくおいしい」と太鼓判を押す。
可児ッテには、この缶詰が並ぶ。「絶滅危惧種から、少しは外れたかな」。存在を知らなかった若い世代の再評価を纐纈さんは喜んでいる。