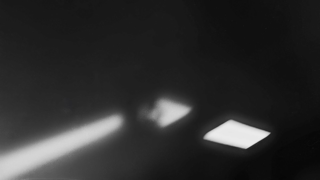「あのこと」をこのエッセーにしようか、ずっとキーボードを弄(いじ)りながら考えあぐねていた。過ぎたというにはあまりに生々しく、でももうけっして渦中ではない、そんな生傷のような思いを、文章にするとき、いつもためらう。そしてその思いを試しに短歌にする。するとびっくりするほど想(おも)いはさらさらと溢(あふ)れて、知らないうちに少しだけ現実を風化してくれる、その作業が好きで、ずっと短歌を書いているのかもしれない。
私性の文学という短歌には、作者と作中主体という言葉がある。作者はその通り、書き手。作中主体はその書き手が書く、主体だ。大きく括(くく)るとこのようになり、書き手が書く主体はイコール書き手と思われるのだけれどそんなことはない。作中主体は作者が演じたい作者の姿だったり、そう見せたい姿だったり、むしろ人間ではなく水だったり、空だったり、犯罪者だったりすることだってありうる。ニアリーイコールと見せつつ決してニアリーイコールとも言えない世界なのだ。

現実世界で悶(もだ)えることは生々しい。けれど短歌という舞台で比喩として森に彷徨(さまよ)うことは少しばかり容易で、私はだから短歌に救われてきたのかと思う。現実を真正面から見ず、ほんの少し自分の目線にカーテンをかけてあげること。もし私が短歌というカーテンの言葉を持たず、丸裸の散文の言葉に10代のときに向かい合っていたら、すぐさま壊れてしまっていただろう。
そうして現実を「五七五七七」で変形させて、誇張して、歪曲(わいきょく)して、風化させる。そのつけは必ずやってくる。「あのこと」と書いたのは書き終わったあとの苦しみのことだ。そう詠まなければ生き延びられなかった私が、自分の書いたまじないに裏切られるとき。愛していた人は私を支配していた人で、憎んでいた人こそ正義で、夏があまりに涼しかったと詠んだことは何も食べられなかったからだと気づくとき、短歌というまじないは私こそが私を騙(だま)していたことを明らかにする。言葉は呪いだ。言葉は罪悪だ。でもその罪悪を使わないと生き延びられなかった。
ほら、キーボードはいつも地獄につながっている
のぐち・あやこ 1987年、岐阜市生まれ。「幻桃」「未来」短歌会会員。2006年、「カシスドロップ」で第49回短歌研究新人賞。08年、岐阜市芸術文化奨励賞。10年、第1歌集「くびすじの欠片」で第54回現代歌人協会賞。作歌のほか、音楽などの他ジャンルと朗読活動もする。名古屋市在住。