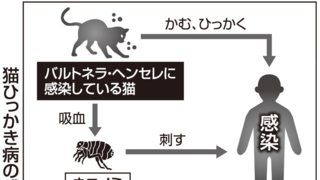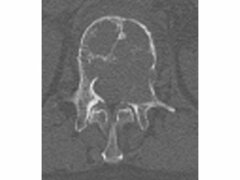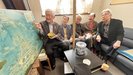岐阜大学精神科医 塩入俊樹氏
一般に小児期の子どもには、周りが見えなく不注意で、落ち着きがなく、移り気で、飽きっぽく、急に思い立って後先考えない行動を取る傾向があります。特に、男の子の成長過程のある時期では、決して珍しくはありません。通常、このような行動のあった子どもも小学校に上がる頃には、少しずつ落ち着くようになり、授業中も座って先生の話を聞けるようになります。しかし、年齢や発達に不釣り合いな不注意や多動性、衝動性といった症状のために、日常の活動や学習に著しい支障を来すことがある場合、「注意欠如・多動性障害(ADHD)」の可能性があります。
ADHDの診断基準では、不注意や多動・衝動性に関連した症状が、年齢または発達水準に対して過剰で、12歳になるまでに見られることが必要とされ、不注意優勢型、多動・衝動性優勢型、混合型の三つのタイプに分けられます。年齢を経るに従い、症状が治まる傾向にあるとされていましたが、最近の研究では、成人期まで症状が残る人が約6割もいることが分かっています。
また、大人のADHDが示す症状は、小児期とは異なり、多動・衝動性が弱まり、不注意が目立つと言われています。では、不注意や多動性、衝動性によって具体的にどんな問題が生じるのでしょうか。
病的な不注意で生じる学校生活での問題としては、忘れ物が多く、ボーッと話を聞いていないように見える。授業にすぐに集中できなくなり、気が散りがちで容易に脱線する。それでいて、興味があることには集中しすぎて切り替えができない。行動が遅い。学校の課題を続けられずに嫌がる。作業も乱雑でまとまりがなく、加えて不正確、字が乱れる。持ち物の整理や長時間の読書ができない。同じことを繰り返すのが苦手などがあります。
また成人のADHDでは、講義や会議に集中し続けられない。一連の課題を遂行することが必要な報告書や書類・資料の作成・チェック・整理が苦手。時間の管理ができない、締め切りを守れない。折り返しの電話、お金の支払い、会合の約束を忘れてしまうなどが問題となります。
一方、小児期における過度の多動性、衝動性では、席にじっと座っていられない。居なければならない場を離れてしまい、待てない。多動や不適切な状況で走り回ったり、高い所に上ったりする。体を動かすことを止められない。静かに遊べない。他人の活動を邪魔したり、ささいなことで手を出したり、大声を出してしまう。順番やルールが守れない、他人の物を勝手に使うなどがあります。
大人では、持ち場を勝手に離れる、会議に長時間とどまれない。会議中に自分の発言の番を待つことができず、他人の言葉の続きを言ってしまう。他人のしていることに口出しをしたり、横取りをするなどの問題行動が生じることがあります。
次回は「限局性学習障害」についてお話しします。
(岐阜大学医学部付属病院教授)