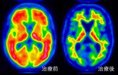所狭しと魚が並ぶ市場をせかせかと歩き回る年配の男性。「キヨシさん、おはよう」。声が掛かると、冗談で返しながら品定めに入る。鮮魚店の一日は、朝の買い付けから始まる。
岐阜市真砂町の忠節橋通りにある「魚喜(うおき)」の店主広瀬邦明さんは、市場では「キヨシマル」の通称で知られる。80歳という年齢を感じさせず、店でも働きづめ。注文を受けてから刺し身や切り身にする昔ながらの商いを貫く。「パックで並べたら、スーパーと一緒になってまう」
創業は戦前。南方から復員した先代の政一さんが岐阜空襲の焼け跡で瓦の山をどけて再開した。18歳で家業に入った広瀬さんは流しを挟んで父と向き合い、包丁の腕を磨いた。
当時は東京五輪(1964年)や翌年の岐阜国体で景気がよく、西柳ケ瀬に近い店は大忙し。料理旅館も始め、マグロなら1匹買いした。長住町の旧市場では、「担ぎ屋」と呼ばれた人たちが愛知県の浜から電車で運んだ近海、磯ものを仕入れた。型にはまらない、雑多な魚が多かったという。「何でも売れる時代やった」
だが、スーパーに客が移り、正月のブリや中元の鮎といった季節需要も下火に。コロナ禍でスナックや居酒屋の顧客も途切れた。それでも常連を思い、イセエビからイワシまで、つい仕入れ過ぎる。「趣味でやっとるようなもんや」
同じ通り沿いで、繊維問屋街の近くにある「うをじゅう」(同市長住町)は、50年に開店した。「バブル期は問屋街の人たちの実入りがよかったから、よく買ってくれたね」と林啓輔社長(68)。価格はやや高めながら、目利きが厳選した魚を求めて遠方からも客が来る。
「脂がのったカツオは尾が白い」。見極め方を指南した先代の太作さんは「魚は季節に正直や」が口癖だった。魚ごとに旬があり、魚を通して季節が感じられる。「だからいい」
こうした魚を知り尽くした個人の鮮魚店は減少の一途だ。岐阜水産物商業協同組合によると、昭和30年代に250~300人いた岐阜市と周辺の組合員数は、ちょうど100人。大半は料理店や仕出しへと業態を変え、従来の小売りを続けるのは10人前後にとどまる。
「後継者不足や売り上げの低迷。形を変えないと生きていけないようになった」と遠山宏紀理事長(67)。岐阜の地では「街の魚屋さん」は今や希少な存在になっている。