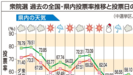夕日が伊吹山にかかる頃、自宅を出て揖斐川に向かう。青いヨシ原に沿って舟をゆっくりと上流へ。狙うのは、海から上ってくるサツキマスだ。
サツキが咲く5月初旬に姿を見せるので、この名で呼ばれるサケ科の魚。「大潮の1~2日後、急に出てくるわ。鮎を追ってくるんや」とかじを操る小林大吉さん=大垣市=。商店を営みながら漁師を続けた父親に教わり、鮎やモクズガニを捕ってきた。86歳の今も現役で川に出る。
星がまたたく中、真っ暗な川面に高さ4尺8寸(約1.5メートル)、長さ約50メートルの網を川を横切るように流し入れる。長良川の漁師に倣った「流し網」の漁法で、網が魚を囲う円弧状になるよう竿(さお)で巧みに舟を操り、しばし流れに網を任せる。
下ること10分。引き揚げた網に銀色の魚体が輝いた。12日夜は3回流して2匹。岐阜市中央卸売市場の初ものになり、1匹8000円の値を付けた。
サツキマスはもとはアマゴで、雌を中心に一部が海に下って再び川を上る。木曽三川でも本流にダムがなかった長良川の豊かさを象徴する魚だった。それだけに、1995年の長良川河口堰(ぜき)(三重県桑名市)の運用開始時は影響が懸念された。
運用開始の翌年、岐阜の市場の木曽三川産の入荷数は2011匹に上ったが、昨年はわずか16匹。うち13匹は小林さんの揖斐川産で、長良川産は3匹だけだった。不漁が続き、羽島市のサツキマス漁師大橋亮一(故人)・修さん兄弟らが手がけた「トロ流し網漁」は長良川で途絶えた。ほぼ同じ形の漁を受け継ぐ小林さんも「昔は1回に7~8匹掛かったこともあった。もう幻の魚や」と嘆く。
「減少の理由は、ものすごく複合的」。長良川でサツキマスのDNAや放流魚の再捕率を調べている京都大学生態学研究センターの佐藤拓哉准教授(生態学)は、複雑な生活史に注目する。
海に下る個体への成長に必要な餌になる虫を育む上流の森林環境、下る途中の川の水質、海の温暖化や餌の魚の減少、河口堰の影響…。どの要因が強いかは分からないが、上流から海へ、そして再び遡上(そじょう)する長い旅路のそれぞれで、取り巻く自然がダメージを受けていると感じている。
「海と川と森がつながっているからこそ暮らしていける生き物の代表がサツキマス。生息環境をつくることは、多くの他の生き物が生きることにもつながる」。小林さんが「川の王様」と呼ぶ魚の命運は、川の行く末と重なっている。